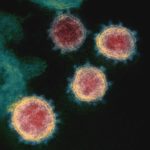日本の医療をささえるもの
- 2020.09.12
- からだ・健康

日本の医療は先進国でも高水準といわれるけれど、今回初めて本格的な疾病治療を体験することになり、「高水準」の意味が理解できたような気持になった。もちろん医療現場も各種検査、診断機器や方法論、先端治療機器や投薬の進歩によって、10年単位でみるとそれこそ世界が変わっているようなそんな日進月歩の進化ぶりなのはよく理解できる。病院施設そのものも近代的でクリーンなものに生まれ変わっていますし、国家単位での医療コストが跳ね上がるのもやむを得ないと思わざるを得なかったけれど。
其の中でも、自分自身が疾病の診断から入院や治療、手術のプロセスのなかで強烈な印象を持ったのが、圧倒的な高水準の医療サービスだった。それは、医療現場の医師や看護師、栄養士や補助員にいたるまで、常日頃アメリカナイズされた接客になれてしまった身としては驚くべきことだった。マクドナルドが日本に持ち込んだ米国流の規格化されたマニュアル通りの接客には、ハートが伴わない違和感があって、今ではコンビニやあらゆる社会の接客シーンで慣れっ子のなってしまっているけれどね。
サービスを提供する側と受領する側の関係をスムーズにしたいというのは常に社会のテーマだと思うけれど、その答えが今のマニュアル通りのものだとするならば、違和感が消え去ることはないだろうと思っていた。ところが医療現場には、全く別の世界があったと思えたほどだった。
2年後の還暦を前にして、いままで病気らしい病気をしなかったし、入院手術は48年前の盲腸一度だけ。医者嫌いで多少の痛みや不調は我慢してしまって、何よりも治療によって時間の速さ(生活のリズム)が変わってしまうのが嫌だった。でも、流石に癌と言われてビビッてしまい、観念して医療に頼るしかないと・・・。
癌患者となって、結石による胆嚢炎がみつかり、そして腹部大動脈瘤まででてきてしまい、かなり臆病になった。もちろん病気そのものに怯えたわけだが、気が付くと身体的な部分と同じくらい精神的に弱るということを自覚し始めた。思考がどんどんネガティブになって、時として自分自身では立て直せないような状況になったとき、家族(女房)の支えは有難かったけれど、日本の医療には実に様々な支えがあった。
医療現場にも実に様々な人間関係が生まれるし、そこに従事する人たちは患者の苦しみや生死に直面している仕事にもかかわらず、明るく振舞っていたことが大きな救いとなった。「こんな世界もあるのか」と思いながらも、その中で徐々に怯えの気持ちが和らいだし、日々個性との出会いや触れ合いを感じることができて、恵まれた環境で治療を受けることができたと思う。
なので怯えの心を癒してくれた印象に残る個性を書き留めておこうと思った次第。
担当医師との絆ができた
胆石による胆嚢炎が悪化して真夜中にERに飛び込んで緊急入院となった6月初め。炎症の状態をみて手術ということになり、外科のM医師が担当と決まった。アラサーの若い着任早々の医師でどちらかというと理屈っぽそうな愛想のない医師という印象。なぜか他の医師とは違う白衣をいつも着ていて、ちょっと尖った感じかな?とも感じた。
入院後抗生剤投与の期間にできるだけ看護師たちの印象を聞いてみると、着任早々でよくわからないという・・・。その「よくわからない」ということに返って興味がわいた。
診察は思った通り理屈っぽくて、持参したタブレットで診察の前に予習したりして、毎回胆嚢炎に関する専門用語をいくつか仕込んだ。すると、診察の会話が徐々にスムーズになり、さらにM医師が同じ大学の後輩であることが分かると(もちろん学部は違うけれど)、共通の話題もできて親しくなるのにそれほど時間がかからなかった。
「炎症が収まらないのでリスクを取って強引な手術はしない方がいいと思います」
「難しい?自信なし?」
「いや、そういうことではなく、やるからにはできるだけリスクが少ない方が・・・という意味です」
「じゃどうするの?」
「ドレナージをして炎症を抑えることにしましょう。胆嚢に管を刺して・・・」
「わかりましたけど、どのくらい時間がかかるの?」
「おそらく1か月くらいは・・・。その間に退院して日常生活してもらえますか?もちろんバッグをつけたままですけど」
「わかった、頑張ってみるよ」
というわけで、一週間後に退院して一カ月半後の8月の初めに再入院となった。
現代の手術のリスクというのは執刀医の技量不足よりも術中、術後の合併症が大きい。腹腔鏡にしろ開腹するにしろ、内臓を空気にさらすことで生じ得る合併症もあれば、喫煙者などは肺機能低下による肺炎が大きなものの一つ。もちろん、何枚ものペーパーと口頭で説明され、手術前には承諾書にサインさせられるわけだが・・・。俺の場合は長年の喫煙習慣が問題になった。少なくとも術前3週間から1か月は禁煙、断煙が必要と。
しかし前週にブログを書きながら無意識に、膀胱癌になって以来の禁煙を3か月ぶりに破った。そして手術までに5本の喫煙をしたことをM医師に報告したら「それはまずいですよ」と叱られることに。
「どうして、何がダメなの?」
「それは説明したでしょう?何度もやりましたよね?」
「そうか?けれど俺は納得できなかったしなぁ・・・」
「またまた・・・、それに麻酔医が絶対に100%拒否しますよ」
「手術明日だろう?それでも拒否?」
「しますね、確実に」
「明日の日程を来週に延ばして、それまでに(外科)部長とねじ込んでみます・・・多分ダメだろうけど」
「揉めるならいいよ。いったん退院後リスケして3週間後にやり直そう」
というわけで、さっさと引き払って退院してしまった。
どうしてあれほど言っておいたのに守ってくれなかったのですか!と何度も言われたし、いつも穏やかなM医師の表情は強張ったままだった。術後の合併症の中でも肺炎は麻酔科の責任を色濃く追及されるらしいから、今は徹底的に麻酔医は拒否の姿勢を取ってるみたいだった。全身麻酔による手術は肺自律呼吸も停止する。なので、その間に肺の持つ浄化作用が失われて痰がたまり雑菌によって炎症を起こすのが肺炎。
喫煙者の場合は肺機能が低下しているので、この合併症の発生確率が高く、場合によっては死に至ることもある。それが怖いのだと。
「そうは言うけれど、生活してて、仕事とかしてて、習慣になった喫煙をやめられないということもあるよ。そういうことも含めて人間は体にいいことばかりやってないし・・・。健康的と言われるものの裏には副作用だってたくさんあるでしょ。」
自分のことを言っただけなのだ。ザラ場をやってたり、ストレスを感じることも多々ある。それにモノを書くというのも同じこと。習慣性があるから理屈通りには行かないと主張もしたし、改めて仕事(株やブログ)も説明したりした。
「おっしゃることもわかりますけど・・・」
「じゃ、急患が喫煙者ったら手術しないの?」
「それはやります」
再入院のこの時は、新型コロナの合間を縫ってようやくスケジュールができ、医師とスタッフ(手術はチームで行う)ので、それぞれのスケジュールを合わせることさえ大変なのはわかっていた。しかし、喫煙がハイリスクであるという根拠も示せていないのも事実で、例えば肺癌の発症率上昇とか今回の新型コロナの重篤率の上昇とか、喧噪されるだけで(因果関係の)実証はされていないに等しい。そして、新型コロナ感染率は喫煙者は約1/3に低下しているという報告が欧州や米国で出ているのに、徹底的に無視されているという事情もあった。
結果的に再入院はリスケジュールのために退院となってしまい、M医師との気まずい雰囲気の中、病院を後にした。
ようやく新たな手術日程が決まり、でも前日に胆嚢の炎症が悪化して緊急で外来診断を受け、そのまま入院となったときM医師が言った。
「僕もね、いろいろ考えさせられましたよ。(お話が)効いたんですよ。それでずっと考えて、そういうこともあるなと」
「悪かったね、俺のせいなのに」
「いえいえ、それも正論だなって思えました」
そういってM医師との関係は一気に改善したし、以前よりもざっくばらんに話ができるようになった。そして腹腔鏡でダメなら無理しないで即開腹でいいから」と言って互いの了解のもとに手術に臨んだ。この時はM医師への信頼はゆるぎなかった。
執刀医はM医師で助手に3名の医師とオペ看3名のいわゆるチーム医療が始まった。開始直後、48年前の虫垂炎手術の悪影響で膨大な癒着が腹部に残されていてその剥離だけで1時間半を要し、さらに胆嚢・胆石摘出をすべて腹腔鏡下で行うという3時間の難手術となった。しかもドレーンが胆嚢を突き抜け、肝臓からでた胆管までもが炎症を起こし肝機能がかなり低下してしまった中での手術だった。
手術後、オペ看護の一人から話を聞いたけれど、胆嚢まで総癒着状態で手術室に声が上がったこと、開腹がベターという意見も他の医師から出たこと、できる限り頑張ってみますとM医師が奮闘してくれたこと、に涙が出た。ちなみに胆石は直径4センチもの大きなものだった。
「やりましたね」
翌日麻酔から完全に醒めた後、そう声をかけてくれたM医師の晴れやかな表情が印象的だった。
ドラマに出てくる女医さん?
術後2日目の午前中にようやく体に装着された様々な機器類が外され、点滴だけとなって術後の姿勢を変えられない地獄のような時間から解放された。バイタル管理のための様々な機器や酸素吸入器、尿排出の膀胱ドレーンやフクラハギの血栓防止のための自動マッサージ器までが装着されていた。
全身麻酔に落ちてしまう手術は痛くもなんともないばかりか何も覚えていないので、僅かながら記憶が寸断されるだけ。なので患者にとって最も苦しいのは身動きが取れない術後だということも分かった。
解放されて間もなく小走りの大き目な足音が病室に近付いてきたかと思うと、いきなり扉が空き三十半ばほどの女性が近づいてきた。そしていきなり、「見させてね」と言って手術用の着衣を捲り上げてテーピングされたヘソの穴(腹腔鏡本体はヘソから挿入する)を眺めてた。
「出血すくないわね」
「癒着結構大変だったのよ。私、開腹したらと言ったんだけどね」
「でも胆石、大きくてびっくりしたよ。私7例目だけどダントツ1番よ。こんなの初めて」
「見た?そこにある」
枕元においてあった摘出胆石を取って
「ほら、大きいね」と目の前に差し出した。
「M先生がんばってたわよ、私は助手に付いたのね」
ここまで一方的にしゃべって、ようやくこの人も医師なのだ、と気が付いた。まるで昔からの知り合いのようなある意味馴れ馴れしい口調と入室から手術跡を確認するまでのガサツな態度。医龍やドクターXに出てくるような女医さんを気取ってるに違いないと思い、笑いが込み上げた。
「どうかしました?」
笑いの理由を問われたところで、言えるはずもなく、腹部に力が入れられて元気なら「私、失敗しないのでって言ってみて」とジョークで返したところ。
それでも彼女のフランクな態度は妙に心地よかった。回診と称して部下を引き連れて回る外科部長の偉そうな態度より100倍マシだ。けれどそれもこれも、医療ドラマやコミックのような世界って大なり小なり本当にあるんだと思えて可笑しかった。
3日目に再度病室に来てくれた時、前回のときの感想を話してみた。
「先生が私、失敗しないので、って言ったらそのまんまドラマになるよ」
「それは無理よ、自信ないもの」
「術後に成功した患者に言うのは嫌味でしょ。術前はあり得ない。でも・・・言って欲しい?」
「今回は遠慮しましょう」
「あのドラマ以来、そういうリクエスト多いのよねぇ」
もしもこのS医師が担当医になったなら、その患者は屈託のない明るさに癒されるだろうな、と思った。馴れ馴れしい態度、ということはある意味患者と同じ目線に立って話してくれるということにつながる。そうすれば少なくとも親しみがわくし、そのことが信頼関係につながるだろう。病院内には一人くらいドクターXのキャラが必要なのかもしれない。
でもねぇ、S先生、キャラが立ち過ぎだよ(笑)
四人姉妹と名付けた若きナース達
膀胱癌の術後のBCG治療が終わってほどなくして胆嚢炎の炎症でERに駆け込みそのまま緊急入院となって炎症を抑える治療に突入したわけだけど、最初は消化器内科の扱いだったこともあって、内科病棟に入院した。そして約8日間、抗生剤や鎮静剤、胃壁保護剤等の点滴治療を行ったわけだが、毎日点滴だけで、ただ寝ていろと言われても・・・という感覚だった。
入院中は日勤、夜勤のローテーションでほぼ毎日看護師さんの顔ぶれが変わるので、同じ看護師さんになったのは僅かに4回だけ。もちろんどの方も、そして最近増えてきている男子の看護師ともに親切に対応してくれたのは違いないけれど、やはり男子の場合は当然一定の距離間がある。でも、たまたまかもしれないけれど、この時は女子の看護師さんはみな若く、しかも失礼だけど新型コロナでマスク必着ということもあり、みな可愛らしい方達だった。
朝晩決まって引き継ぎ後に挨拶にきてくれて、本当に痒い所に手が届くような医療サービスを提供してくれたわけだが、2度担当してくれた4人の看護師さんを四人娘と名付けた。
看護師さんの仕事ぶりを見ていると、昼はひっきりなしにナースコールがかかるし、夜間は2時間の仮眠はゆるされるものの、少人数で頻繁に対応しなくてはならない、想像をはるかに超える重労働だな、と思わざるを得なかった。2回目の看護師さんとは遠慮なく会話することができ、また看護師さんも時々愚痴が出るようになってくるし、時間が空くといろいろな話を聞きに来てくれる。
若いから点滴の針も上手くさせなくて、採血もあるから、結構な頻度でルート確保(針を刺す医療用語)しなくてはならないが、俺の場合はなかなか静脈が浮かばずに何度も失敗をする。真剣な眼差しで懸命の作業のわけだが、上手くいかなくて「ごめんなさい」を連発する看護師さんも。そんな時「何度でも刺せばいいよ。練習しちゃえば」と言ってやる。娘と歳も近いせいか、そう、まるで自分の娘みたいな感覚になってくる。
感動したのは胆嚢ドレナージの時、強烈な痛みに必死に耐えていた俺の手を握ってくれたHさん。麻酔というか痛み止め程度の麻酔を皮膚の表面に塗っただけで(多少の効果はあるのだろうけど)、横向きになり胆嚢にドレーンを刺すわけだから痛くないはずがない。モニターで確認しながら深さを調整するのだけど、その度に激痛が走る。位置が決まったら脱落防止のために縫合して完了という30分ほどの外科治療だけれど、「あれは痛いんですよ」と親身に看護をしてくれた。
もちろん彼女達は担当のどの患者に対しても同じように優しく接している。なので自分が特別とは思わないけれど、2度目には「患者さんは話も上手いし、面白いし、楽しい」と言ってくれた看護師さんもいれば、看護師の仕事に対してやりがいを語ってくれたり、身の上相談までしてくれる看護師さんもいた。
以前事業をしていた時、多くの若い女性社員を抱えていたけれど、本当に社員教育は難しかったことを思い出した。そして、なぜ若いのにこれほどしっかりした理念を持ち、行動できるのだろうと本当に不思議だった。「プライベートではそんなことないですよ」とあるベテラン看護師は言っていたけれど、いやいや、職場で立派なら何も問題ない。
そして、このナース教育こそが、日本の医療を支える根幹の一つだと確信に至った。
退院の前日、自主的にドレナージ用のバッグ(私品)を持ってきてくれて、「これ、良かったら使ってみてください」と言われ、ありがたくいただいてその後の3カ月近くのドレナージ生活を支えてくれた。退院当日は2人が夜勤明け、2人が日勤というタイミングだったらしいけれど、4人揃って見送ってくれた。
もちろん今回の入院時に内科病棟まで挨拶にいったら3人が日勤で、わずかな時間だけど集まってくれた。昔から気弱になった患者からは「白衣の天使」と見えただろう。その気持ちがよく分かった闘病生活だった。看護の仕事は辛いことも多いだろうけど、頑張って欲しいと願うばかり。
ベテラン看護師の芸風?
術後2日目、突然病室に現れたベテラン看護師のTさん。当日の日勤担当だったわけだが、いつものような型通りの挨拶代わりに、
「傷の具合を見せてくださいねぇ」
といきなり近寄ってきて、「ちょっといいですか」と言いながらやおらパジャマを捲り上げ、「近くで失礼しますね」というとヘソ上空15センチの高さまで顔を近づけてきた。
「(なんだ?この人は・・・)」
と思いつつ声が出ないでいると約30秒ほどヘソの傷を凝視していた。そして、
「はい!順調ですね、出血も少ないし」
と言って病室を去った。
午後になって予約しておいた初シャワーの時間になると、15分前には病室に現れて、こまごまと世話女房のように着替えとタオルをチェックし、それをまとめると抱えて、
「では、行きましょう」
ときた。仰せの通りシャワー室に同行してもらって、シャワーの使い方をレクチャ。お湯加減を見て、
「さぁ、どうぞ」
「大丈夫ですよ、初めてじゃないので自分でやりますから」というと、「そうですよね」と言いながら、今度は腹腔鏡の傷跡回りのお湯のかけ方、流し方を説明し始めた。だまって聞いているわけにもいかず、脱衣しようとするけれど、Tさんはシャワー室から去る気配なし。
「脱ぎますよ」と声をかけると
「どうぞ」
ときた。どうぞと言われてもねぇ・・・。仕方ないので、Tさんの目前で全裸に。するとそれを待っていたかのように、
「シャワー中にボタンを押して読んでくださいね。状態を確認しますから」
といってようやく退出。
入院・手術となれば、看護師さんに術前の剃毛や浣腸でお世話になるし、浣腸後のトイレの状況まで確認される始末だから、こういう状況には慣れないわけでもない。それでも、やはり見ず知らずの異性の目をどうしても意識するでしょ。医療の現場ってそういうことを意識したらいけないのか?なんて思いながら髭を剃り、洗髪をしてナースコールした。
すると、遠慮なく浴室の扉が空き「入りましたね」と声がかかった。
そして例によって至近距離まで顔を近づけてヘソの傷を凝視。
「(近い、近すぎる・・・、見られてる・・・)」
「はい、大丈夫ですね。気持ちいいでしょ。ではごゆっくり」
と声かけして去っていった。
意味わからん!
シャワー後、1時間ほどして血圧・体温測定で現れたときには、
「お通じありましたか?」
というので、
「いったけど、息張れなくて・・・」
「そうそう、私も経験あるんですよ。私ね、2度の出産を経験してるんですけど、2度とも帝王切開で・・・」
と言いながらベッドの横でいきなりたけしのコマネチポーズ!脚を蟹股にして中腰になって両手でコマネチ始めちゃった!
「2回ともでしょ。帝王切開って傷も大きいんですよ。だからお通じ本当に大変でしたよ。息張ると傷が開いちゃいそうで・・・。気持ちわかりますもん」
俺はね、あなたのそのコマネチの気持ち、分らんよ!
でも思わず爆笑でお腹は痛いし、参ったね。
はきはきと物は言うし、てきぱきと仕事もこなす。採血なんかは一発で手際よくルートを確保するし。いかにもベテラン看護師さんという雰囲気のTさん。でもね、男性患者の前で看護師さんがいきなりコマネチですから。貴重な体験だったなぁ・・・。まさかこの看護師さんの芸風ってわけでもないのだろうけど。
気持ちが揺れた美人ナース
今回入院して、肝臓の炎症の悪化を防止する意味で、術前に胆管ステントを施すことになった。胆液は肝臓で生成された後、消化が始まると胆管へと放出される。けれども量的な調節機能がないから胆管の中間部に胆嚢を設け、普段からそこに一時貯蔵して排出量を調整するのだ。つまり胆液は胆嚢で生成されているわけではない。
だから胆嚢を全摘出しても、慣れてくるとある程度柔軟性が出てきて対応できるらしい。俺の場合、胆管は十二指腸に接続しているから、胆嚢の炎症による腐った胆液や汚物によって胆管が目詰まりを起こしていた。その解消のために、内視鏡(胃カメラ)を使い、胃から十二指腸まで進行してそこまでプラスティック製のステントを運び、胆管にステントを装着するわけだ。
どうやらKさんは、そのミニオペに参加していた看護師さんらしかった。
術前にも担当看護師でないのに病室に顔を出してくれたし、結構気安く話せるようにはなっていたが、何せ皆マスクをしているのでまず顔を覚えることは不可能で、声と素顔のイメージを一致させることはできない。それでもいやらしい言い方をご容赦願えれば、何ともしとやかな身のこなしと艶っぽい声が魅力的だと思った。スタイルもよく、ちょっと前髪が乱れているところなど、ど真ん中のストライクという感じで・・・。
術後3日目の午後、歩行練習をしているとき、長い廊下の前方から小走りに近付く看護師さんがいた。
「退院ですってね、おめでとうございます」
といってマスクを取るといきなり彼女の方からハイタッチ。横に点滴をした患者さんがいたけれど、ちょっぴり優越感!けど、なぜマスクを取ったのかわからず、また誰なのかもイメージできなかった。そう、あまりに美人というか、バットを一度も振らずに3球3振という感じ。手にハイタッチの感触が残って・・・。少しして、胆管ステントの看護師さんであることに気づいたときにはすでに去った後だった。
でもね、そんな、院内でハイタッチなんかしてるシーンは見たことないしね。
なんて書いたらいいのか、あれはいったい何だったのか・・・。本当に素敵な看護師さんだったな。
性同一性障害のお掃除係さん
今回の入院でもう一人とても気になった方がいた。毎日午前11時ころ「お掃除します」とだけ言って部屋に入ってきて床をモップで掃き掃除し、ごみ箱を片付けてくれるお掃除係さん。黙々とお掃除して帰ってゆく。最初は男子の障害のある方かな?程度に感じて、2回目は障害があるのではなく寡黙なだけかな?と思い、それでも真面目に大病院で清掃員をやってるって偉いなぁと。
3回目も「お願いします」と言って掃き掃除をしている後ろ姿をベッドから眺めていた。そして前かがみになって背中のユニフォームに張りが出来たとき、
「うん、女性用下着?女性?」
とはっとした。
自分のことが精いっぱいで、気にする余裕もなかったけれど、どう見ても男性で、男性としての身なりや振る舞いをしていたので気にすることもなかった。けれど、トーンが低くて気付くことはなかったけれど声そのものは優しかったからね。
最も親しくなった看護師さんにそれとなく聞いてみると、絶対に私から聞いたって言わないで欲しいのですけど、と前置きして、
「確かなことは分らないですけど多分GID(性同一性障害)かもしれないですね」
と答えてくれた。こちらも変な意味はなく、差別意識も微塵もなかったので
「意図はないから安心して。ただ疑問に感じたことを確かめただけ」
と言った。
「うちの病院はそういう方を積極的に受け入れる方針なので・・・スタッフやドクターにもLGBTの方はいらっしゃいますし・・・」
それ以上の会話はやめた。あまりに問題がデリケートで微妙だからだ。入院患者は比較的高齢者が多く、保守的な考え方の人が多いだろう。そういうところで会話を聞かれたりしたら、取り返しがつかなくなることだって十分にあるし、病院側もその辺の配慮は十分にしているはず。俺ごときが興味半分で話していい問題じゃない。
それでも、社会のマイノリティを受け入れて居場所を確保しているという事実は、とてつもなく貴重だと思った。自分の経験の中でも、GIDであるという事実を周囲に公表して堂々と生きている方を一人知っている。男性用のスーツとバッグ、紙は短髪(スポーツ刈り?)にして、堂々と不動産業を営んでいる。
けれどもそんな例は稀で、多くは他人に悟られないように怯えて生きているのかもしれない。そういう人にとって今の社会はあまりに窮屈で生き辛いと思うし、働く機会さえ大きく限定されてしまうだろう。でも、収入の道がなければ生きられないことは厳然とした事実だ。
自分が病気になり、入院・手術でお世話になった病院は、少なくともそういう人に働く機会を提供していると思うと、医療だけでなく社会を支える役割を担ってると思うと、嬉しくなった。見かけ上、社会は許容度と公平感が増しているような印象を耐えるけれど、実際は格差が広がり、不平等感は増すばかり。そんな閉塞感の高まる社会でほっとする隙間を見いだせた瞬間だった。
医療現場の個性と優しさに救われた思い
たとえ癌が進行していて余命を限定されるような状況であったなら、患者や家族の心はもっともっと深く傷つくだろうな、と思う。自分が余命を宣告されるような状況であったなら、表情は曇りっ放しだろうし、そうなると医師や看護師の負担も相当に大きいだろう。
しかし、必要な会話はするだろうし、時には冗談も言うだろう。入院すれば身の回りの世話をしてくれるのは看護師や補助員の人たちなのだし、回診という形で毎日担当医師とのコミュニケーションもある。
怯えた心は時間の経過や入院生活における日々のたわいもない会話によって癒されるのだということを改めて実感した。そして患者にとって「日々の取るに足りない会話」というのが病気の治療にとって想像以上に効果的なのだな、と思うに至った。悲劇が起こっても時間とともに記憶が薄れ、日々を生きることによって忘れる時間を持つことで癒される。だからこそ押しつぶされないで生きて行けるのだと思う。
今回、俺はそうした入院生活で様々な個性と優しさに触れ合うことができて大いに癒され救われた。そして改めてそれが日本の医療を根底から支える「世界最高水準のサービス」なのだと実感できた。
-
前の記事

バブル・ラリーが始まる予感:9月11日(金)後場 2020.09.11
-
次の記事

一文高値警戒相場:9月14日(月)前場 2020.09.14