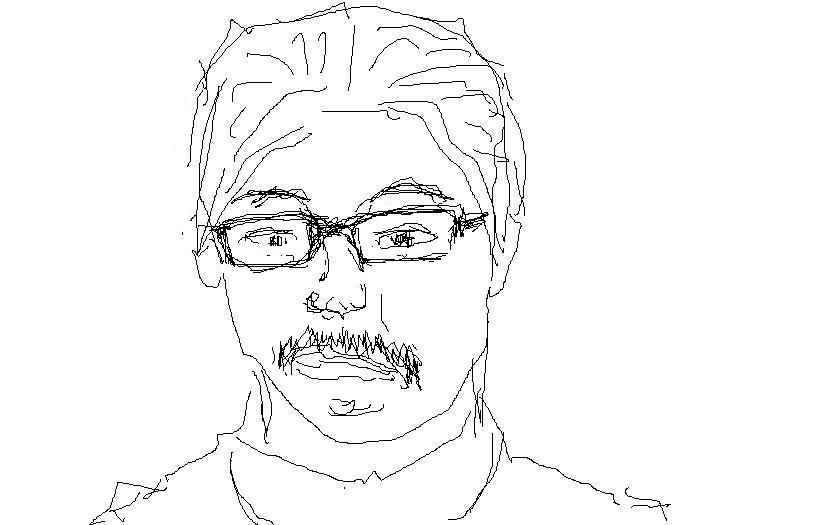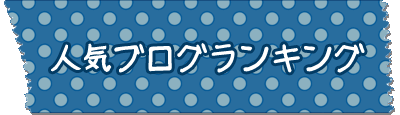現状の資本主義は持続不可能な領域に到達していると思う
- 2024.06.16
- 放言

まともな経済学者ならば、米国経済の今が「景気は悪くない」なんてことは決して言わないし、言うはずがない。米国政策金利が僅かの間にFFレートがゼロから5.500%まで、極めて急激に上昇したにもかかわらず雇用の増加数は(減少傾向にあるものの)堅調な水準を維持し、物価は着実に沈静化する傾向になる、というのは完全に「理論破綻」だからだ。
世の中の著名なアナリストは、米国当局が発表する経済統計や、それに対するFRBの金融政策を分析するのに躍起になっている。けれども若かりし頃真剣に経済を学び、毎晩の美食と美酒の代わりに少しでも、復習をしようと努力していたならば、米国経済は強い!日本株は今すぐに¥50,000を付けてもおかしくはない!などと言うはずもないし、少なくとも今の状況で安易に投資を勧めたりはしないだろう。
自身が持っている経済の知識や経験からして、米国株高を好景気と安易に結び付けたり、肯定するこじ付けを推測して平気でコメントするようなことはしないはず・・・。ここで何故、素直に疑問をコメントしないのだろう?と思うし、そんな「アナリスト」「ストラテジスト」と言った偉そうな肩書が聞いて呆れる。
作為的な米国経済
難しい経済知識が無くても、いやむしろ肌感覚の方が確かなことなど山ほどある。その意味で自分が米国に住み、米国で働いていると仮定したら、クレジットカードの支払金利が20%/年になってまともに生活できるだろうか?と考える。住宅ローン金利も10%を超え、ほとんどアリとあらゆる金利が、かつて日本で騒がれたサラ金、街金のレベルになって、やって行けるだろうか?と思えば、答えは簡単なはず・・・。
そう、今現在個人消費が頼みの綱である米国経済は、終わってる!と思って間違いないと思う。それが真っ当な見方なのではないか?と思う。
最近米国の経済学者たちが皆口をつぐんでいるのは、今の米国経済に対しコメントのしようがないからだ。今年は大統領選挙イヤーでもあり、米国の政治状況は乱れに乱れている。そして痴呆が進み過ぎてまともな判断力が期待できないバイデン政権を維持するために、当局は出来る限り経済指標を脚色している。ただでさえトランプ氏に同情的な風潮にあって「景気が失速してます」と言えば、選挙に勝ち目がない。
これは実体経済とは全く別物の話であって、米国民の大半が「そんなことはどうでもいい」「此の先どうやって生活すればいいんだ?」と思ってるはずだ。働き盛りの20代30代がこの高金利のなかで、学資ローンに追われ、高額な家賃に追われ、住宅ローン金利の上昇に追われ、頼みの綱のクレジットカードの高金利に追われ、BNPLにはまり込む。
政権の財務長官(イエレン)は雇用分析が専門の経済学者だから、雇用さえ堅調であれば大丈夫というスタンス。それに忖度して(というかプレッシャーに負けて)雇用統計を懸命にドレッシングしている労働省労働統計局という図式。流石にFRB・パウエル議長も「こんな茶番に付き合っていられない」というわけで、あからさまに「雇用統計に対する疑い」を口にした。
パウエル議長の疑問
仮に雇用統計のみならず米国の経済指標が実体経済を表す(忖度ナシの)生データであれば、米国経済がFRBの金融政策の想定をはるかに超えて強く推移しているわけで、現時点で利下げの余地はない、此の先もデータ次第、とせざるを得ない。FFレートを5.500にしても雇用は落ちない、株価は下がらない、消費は減らない、となれば、FRBの出番はない。ましてインフレがジワジワと低下してインフレ目標に近づいてくるのであれば、状況を見守るだけである。
地方連銀総裁や理事の合議で決まるFRBでさえ、政治色は如実に反映されてしまう。そのことを含めて、パウエル議長は「現状の政策金利に対し、間違っているのではないか?」と疑問を感じている。それでこれ以上我慢が出来なくなって、会見で雇用統計に対する信頼性の欠如を口にしてしまった。
トランプ政権下で任期満了のジャネット・イエレンに代わってジェローム・パウエルが指名された。100%再任に自信を持っていたイエレンは、バイデン政権になると財務長官に任命される。イエレンはそこで何をしたか?と言えば財政をふかしまくってことごとくFRBの金融政策に抗った。急激なインフレを抑え込むためにFRBは急激な利上げを余儀なくされたけれど、その最中でも財務省は大型予算を次々に繰り出して、金融引き締め効果を奪い去った・・・。
そうした勢力争いに対してもパウエル議長は嫌気がさしているに違いない。ましてトランプが大統領に復帰すれば、また金融緩和の圧力をかけられることは目に見えているからだ。そうした政治的な対立も含めて、そうした権力争いのしわ寄せは全て国民に回ってくる。来年、パウエル議長は再任を拒否するだろうし、トランプは交代の意向だろう。
NVIDIAブームとは?
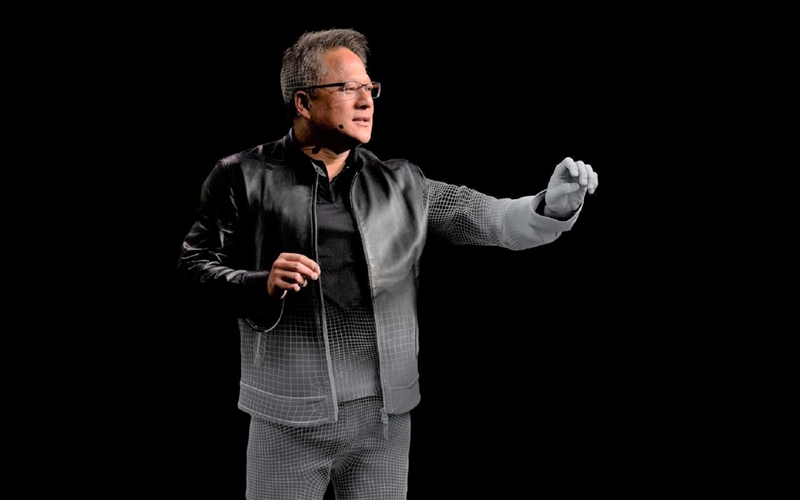
AIブームに沸く米国株式市場。特にハイテクセクターともいえるNSDAQは、株価的には絶好調だ。その市場を牽引するのが言うまでもなくNVIDIA。NVIDIAと言えば、3Dアクセラレータとしてポリゴン処理の高速化に特化したGPUを数多く発表していた。初期の頃の画像処理がアニメに毛が生えた程度の処理しかできなかったが、ゲームなどのスムーズな動きの再生、よりリアリティのある動きや画像の再現に特化して性能を向上させてきた。
そしてある時点から、リアル映像の3Dグラフィクス製作・再生への要求が高まり、そのためには並列処理性能が最も重視されるようになり、GPUに搭載するコア数を飛躍的に拡大する政策を採用した。そこが従来のインテルCPUとの違いで、高い処理能力の少数のコア追及を志向するよりも、能力は低いけれど極めて多くの並列処理が可能なGPUの性能がAIにおいては各段に有利であることが証明された段階からNVIDIAの快進撃が開始された。
例えばスパーコンピュータの「京」などは、高性能なCPUの搭載数を増やし並列処理能力を高めたもの、と言える。そうした状況からNVIDIAは並列処理数を驚異的に増加させることが、AI処理には有益と結論付け、現状は数千の小コア搭載から二桁、三桁の小コア搭載を実現しようとしている。
こうした流れでNVIDIAは吹けば飛ぶような規模の特化型企業から、時代のメインストリームに躍り出て、とんでもない企業に大化けしたわけだ。
半導体のそうした技術転換は滅多に起きるものではなく、これ以上の進化には2nm(ナノメートル)の回路技術は必須で、歩留まりの良い量産化実現にはあと3年はかかると言われている。現時点ではTSMCの独壇場でSUMSUNが追従する形だが、製造装置等の周辺技術が追い付いていないのが現状で、それがAIの核心であるディープラーニングを左右することになる。
こうした状況からも、インテルやAMDから有力な対抗製品が出なければ、NVIDIAの牙城は崩れないだろうし、少なくとも同社の株価はこの時点でまだ、始まったばかり、という可能性さえある。
米国経済は砂上の楼閣
こうしたNVIDIAの半導体ブームが、果たして米国経済の成長を牽引できるか?という疑問の答えは難解だ。現状のAIは恐ろしく広範囲なデータを瞬時に検索し、端的な文章、または画像や動画にまとめ上げることを意味する。それは言い換えれば、ネット上に公開されたあらゆる著作権を蹂躙する行為でもあるために、政治的な制限が掛かることは明らかだ。
また、疑似的にAIがまるで意思決定をしているような錯覚が生じる懸念もあり、人々や企業は、盲目的にAIのアンサーを信じて行動するようになると言われているが、これが正しいのか否かという判断基準を奪い去ることになりかねない。
現在のAIの研究はディープラーニングの発展形として判断能力を備え、疑似的な意思を持たせることに集中している。そしてそうなれば、AIとしての未来予測が可能で、あらゆるリスク管理をAIが担う時代になるということを意味する。
しかしそれには、経済全体を牽引するだけの影響力は持ちえないと思う。何か一つの分野が驚異的な発展を遂げたとして、それが経済全体を押し上げるようになるまでには相当の時間がかかるもの。たとえばインターネットがいい例で、確かに普及が始まってから約30年かかって今のレベルに到達したわけで・・・。AIも当然その程度のサイクルはかかるものと思う。
インターネットは発展したけれど、あらゆる分野で人々の雇用を奪った。ネット以上にAIの発展は雇用を奪い続けるだろう。そうした社会が果たして好景気と言えるのか?は甚だ疑問だからだ。
米国経済は債務とドル安で崩れる?
AIはまだ本格的な実用の初期段階であり、現在の経済状況を変える決め手にはならない。米国は政府歳入を国債利払いが追い越す、または現状で追い越したと言われているけれど、国債総額はエンドレスで増え続ける。いくら何でもそのことが十分に分かっていながら、此の先も米国経済は万全と誰がいえるのだろうか?そしてドルに対する信認はいつまで続くのだろうか?
政府債務のみならず企業債務や個人の債務の驚異的に増加して今日に至っているわけだが、その状況で米国経済は従来と同様に拡大を続けるのだろうか?
作為的な経済指標によって安心感を与えるようなことをしなければ、今の米国経済は支えられなくなっている。すでに中銀の総裁までもが、市場に対し懸念するメッセージを発信せざるを得ない状況を、どう解釈するのかは個人次第だと思うけれど、経済の根幹が萎めば、世の中はAIどころではなくなってしまうのではないか?
それは人類が驚異的なテクノロジーの進化とともに火星に到達したからと言って、何も変わらないのと同じではないか?
日米欧の三極であまりにも政治家や官僚たちの、長い時間をかけて築き上げてきた経済学の見識を無視するかのような傲慢な態度を続けている現状を、株式市場や債券市場はいつまで容認するのだろう?と考えると、そろそろ限界が到来しつつあるという気がしてならないのだ。
-
前の記事

クラウス・シュワブの思惑が世界を破滅させる!? 2024.06.15
-
次の記事

景気後退を織り込む相場が始まった!?:6月17日(月)前場 2024.06.17