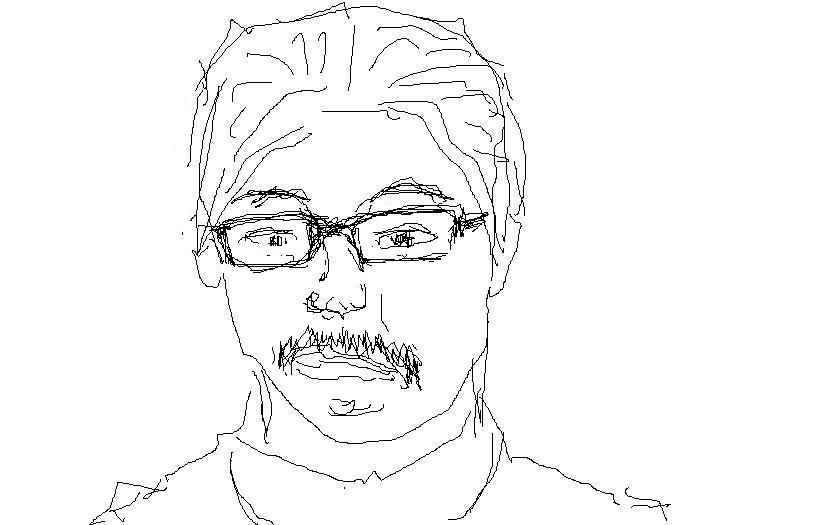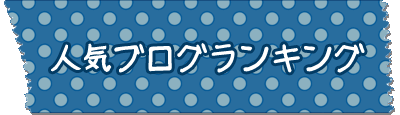こんなにホンダが好きなのに・・・【2代目プレリュードAB型 その1】
- 2025.08.02
- 自動車

誰しも運転免許を取得して、最初に乗った車には思い入れがあると思う。それがどんな車であっても、境遇に恵まれて高級車であっても、必死の思いでローンを組んだ中古車であっても、最初に握ったステアリングに対する思い入れは、生涯消えないものだと思う。
車好きならなおさらで、動けばいいくらいの合理的な考えの人でも、彼女をドライブに誘うのが目的という軟派な人でも、初めて自分の車のステアリングを握るときには、胸が躍ったろう。自分にとってはもう半世紀近く昔の話になってしまうけれど、自分の車に乗れるという事だけで、自由に何処にでも行けるという事だけで、全て満たされていた。
自分が最初に手に入れた車はホンダだった。以来、ずっとホンダに乗り続けてもいいと思うくらい、好きになった。
2代目プレリュードAB型
車を気に入る動機なんて、たわいもないことが多い。学生の頃は特に憧れた車はトヨタ・ソアラとマツダ・コスモだった。どちらもハイソな雰囲気で貧乏学生にとっては、将来的にもとても買えるようになると思えない高嶺の花だったけれど、当時密かに相思相愛だった女友達が、真っ赤なコスモが素敵と言っていたのを思い出す。
けれども、田舎で働き出して足が必要になると、当然身近にあって誰も乗らなくなったようなボロボロの中古車で当面を凌いだ後、欲しくてたまらなくなった車が2代目ホンダ・プレリュードだった。そしてようやく手に入れたのが、濃紺のプレリュードAB型、走行距離45000kmのXZグレード、5MTだった。
購入の動機
当時デートカーとか言われて大流行していたプレリュード。初代は地味なデザインであまり人気がなかったけれどこの2代目からは大変身を遂げた車。けれども当然助手席に乗せる彼女も遠距離恋愛でもっぱらシングル用途だから、そんなことは意識しなかった。
けれど明らかに欲しいと思った動機は、TVCFのバックミュージックの使われたラヴェルのボレロが何とも素敵でそそられたというのが1点。車名だってプレリュード(前奏曲)だから、クラシック音楽のイメージもあったし、自分の人生の前奏曲なんだ、と勝手に解釈もして自己満足に浸ってたというのもあった。
そして決定的だったのは、走行中のプレリュードを後ろから見ると、リアのトレッドが広くて、リアタイヤがフェンダーぎりぎりまで広かったこと。当時の日本車ってみなタイヤチェーン装着に配慮して、トレッドが狭くフェンダーとの隙間が大きかった。デザイン的に凄く不安定感があったし、とにかく不格好だったから。
ホンダの開発チームがそのことを意識したかどうかは分からないけれど、とにかく前後ともにタイヤのおさまりが非常に良くて、日本車のイメージからかけ離れた車だったことが確か。
でも、そのお陰で後日、とんでもない苦労をさせられることになったけれど・・・。
結局好きになった理由なんてそんな程度なんだと思う。専門的には数々の欠点もある車なんだけど、そりゃ恋愛と一緒でいい部分しか見えないし、見てもいない。というか欠点なんかどうでもよいわけです。でもそれが大切なことなんだ、と今になると実感できるのだけど。
ハンドルが動かない!
納車の日って本当に待ち遠しいもの。わくわくドキドキで、中古車ディーラーが自宅まで届けてくれて、初めてキーを渡された時にはもう夢心地だった。早速乗ってエンジンスタート!少し車を移動させようと思ってステアリングを切ろうとすると・・・あれっ?動かないぞ!
勤務先の工場のフォークリフトなんか片手ですいすいグルグルだったのに、なんで?
この車グレードがXX、XZ、XJとあるうちの2番目の5MT車ということで、ノンパワステだった。今ではそんな車に乗った経験のある人はいないんじゃないか?って思うけど、とにかく車庫入れは毎回汗が出るほど。逆ハン切りまくってやっと収めるという有様。彼女を乗せてたら格好悪いだろうなってね。
それでいて走行中は妙に軽くなる。軽くなりすぎて、返って怖いと思えるほど。
でかいワイパーが1本だけ!?
この車、雨になると結構厄介で、雨量が少なければ問題ないんだけれど、多くなってくると何と雨がワイプしきれないんだ。如何せんシングルワイパーなので、ふき取りの感覚が間延びするし、視界を確保するのが難しくなりがち。もっと雨量が増えると、何と車体の左右に雨が飛び散る!
逆に雨量が少ない時、ワイプ間隔を広くすれば、極めて良好な視界が確保できるという利点もあるからね。わかった!大雨の日には彼女を乗せてデートしちゃいけないんだ!って俺には関係なかったけれど。
ゴトゴトと変なブレーキ
今では当たり前の装備になってるABSが、この車にはついていた。ホンダは確か4wALB(4輪アンチ・ロック・ブレーキ)とか言っていたけれど、当時としては先進の技術。いち早く取り入れるなんてホンダらしいけど。
何のためかと言えば・・・危険回避のブレーキイング時にタイヤが簡単にロックしてしまうと、制動距離が伸びて事故につながる。これをロック手前で油圧反力によってブレーキパッドを押し返し、タイヤロックを回避することで、結果的には制動距離が短くなるという理屈。
免許取得したての頃は、運転も下手くそで結構頻繁に危険な目に合っていて、すぐにこの機能を意識することになった。きつめにブレークを踏むと、気持ち悪いくらいゴロゴロと反力が伝わってくる。でも安心なゴロゴロ、ゴトゴトだと思ってた。
ところがある大雨の日、公道上にはいくつもの水たまりが・・・。そして歩道には歩行者がいて、水撥ねさせてはいけないと思いブレーキを踏むと、アンチロックが作動しまったく制動しないという怖い体験をした。要するにブレーキポイントが水たまりの上だったら、即アンチロックになってしまうんだね。以来、アンチロックを過信しないように心がけるきっかけになったよ。
でもドライの路面では、大方の場合ブレーキングでタイヤをロックさせた方が制動距離は短くなる、とBMWドライビングスクールでは教えていた。正確にはビデオを見たわけだけど、これも大半のドライバーはタイヤをロックさせるほどきつくブレーキを踏んだ経験がないらしい。だから危険だと感じたらガツンをブレーキを蹴とばすように踏む訓練を日頃からやっておくべき、というなかなか説得力のある内容だった。
リトラクタブルヘッドタイトがパカパカ!
2,3年したころ、夕方日も暗くなりはじめ、ライトオンしたときにいきなりヘッドライトの開閉が止まらなくなってしまったのにはビックリした。当時のリトラクタブル・ヘッドライトには結構頻発した故障だったらしいけど、走行中にいきなりパカパカ始まると堪らんよね。
第一点灯したままパカパカじゃ走るわけにもいかないし・・・。対向車も何事か?と思うだろうし。知り合いの中古車業者に事情を説明すると、駆け付けてくれて、あっという間に直してくれた。このプレリュードにはよくある故障で原因はアースのショートだという事だったけど。
この時に分かったことだけど、車って言うのは、電装系は全てアースによって守られてるんだということ。エンジン点火のために高電圧な電気を常に使用してるし、エンジン自体のアースは鉄製のボディーで取られてる。けど、何らかの理由によってアースが効かず高電圧が電装品に流れてしまうことが・・・。パワーウインドウ、ワイパーとか、そして今回のリトラクタブルの駆動モーターとかね。なかなか複雑なんだね。
如何せん非力なエンジン
さて米国の極端に厳しく達成はまず不可能とされた排ガス規制(マスキー法!?)に世界で最初に対応したのが、ホンダのCVCC技術だったことは有名で、それがホンダ飛躍のきっかけになったことは紛れもない事実。阪神タイガースの田淵幸一の奥方がなぜかCVCCのシビックのTVCFなんかに出てたけど。
その技術を少し発展させたCVCCⅡという構造で作られた、水冷四気筒横置きエンジンがこの車の心臓部。吸気2排気1の3バルブをロッカーアーム方式で動かすSOHC。燃料はキャブレター方式で供給され、おまけにシリンダーに不完全燃焼ガスを再燃焼させてクリーンするという副燃焼室なるものが付いていた。
エンジン単体では125psを発揮するけれど、今のネット基準(補器類を装着した状態)では恐らく100psも出てなかった思うし、これが軸出力(シャシーダイナモ測定)なら80ps以下だろうなという悲しいエンジンだった。
まぁ噴き上がりはモサモサでいやいや回転が上がるという感じ。でも5000rpmを超えるともう悲鳴が上がってた。キャブレターでバカバカ燃料をぶち込む方式では、これしか排ガスをクリーンにすることはできなかったのだろうけど。
そんなホンダの技術もじきに電子制御燃料噴射方式の登場で呆気なくお役御免になちゃったけどね。
(その2に続く)
-
前の記事

株価急落!米雇用統計に仕掛けられた爆弾! 2025.08.02
-
次の記事

こんなにホンダが好きなのに・・・【2代目プレリュードAB型 その2】 2025.08.03