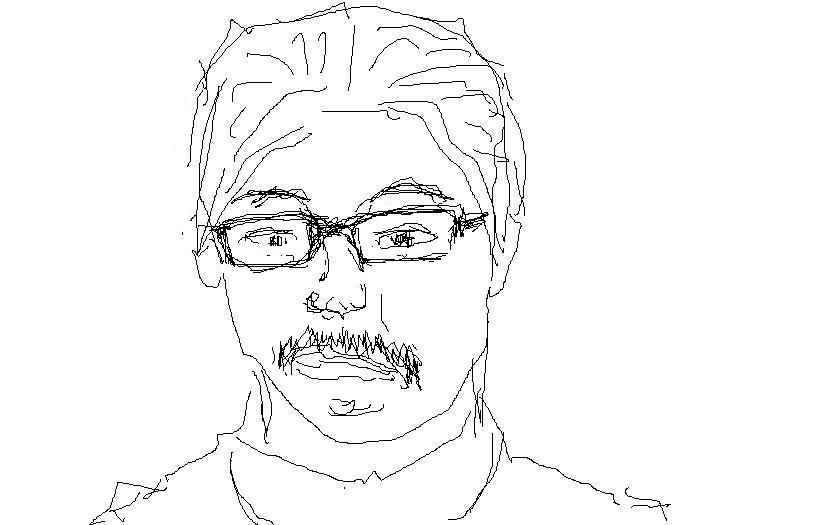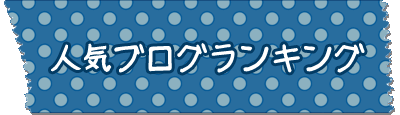株式投資:買いで儲けた時代(10年間)の終焉
- 2019.06.26
- トレード雑感

日々相場に向き合っている身としては、毎日の積み重ねから投資に対するスタンスの変化を微妙ではあるけれども、感じ取っているのだと思う。
自分でもはっきりと意識できるようになったのは、去年の秋頃だったような気がする。10月初めに米国のペンス副大統領の対中批判演説の内容があまりにショッキングで、非常に強く印象に残ってしまったことが、きっかけだったのかもしれないと、今になって感じます。
あの後、年末まで株価は上がり目がなくて、遂にクリスマス暴落へと雪崩れ込んだわけで、あの暴落は明らかにこれからの世界経済を示唆する出来事だったような気がしてならない。
10年間上げっぱなしの株式市場
リーマンショックによる株価底打ち以来、まるまる10年間、米国株式市場はひたすら上昇するだけの過去に例のないような上昇トレンドを作った。
リーマンショック

リーマンショックは2008年9月15日。以来翌年4月の底打ちまで経済システムを破壊するような暴落相場が続いたわけだが、その時、世界中でルール破りが行われ、なんとか窮地を脱したわけです。
CDS等のデリバティブは決済停止、流動性を失って紙屑になった債券を中銀がかき集めて買いとるという金融緩和。しかし実際に行われたのは、残高の数字を変えるだけという荒技。
それでも時間がかかったのは、当事者がどのくらい棄損しているか、把握できなかったからだ。
QE(Quantitative Easing)と言う名の超荒技
結局世界経済を救ったのは世界の中銀によるQE(量的緩和)という禁じ手。何故禁じ手かと言えば、「通貨供給量を極端に増やすとインフレになる」というのが主流の経済学だったから。
そもそも、「通貨の信認」を担保できるか否か、誰にも自信がなかった。
しかし、金融機関に決済資金がない状況では、経済は成り立たないという「背に腹は代えられぬ」状況があって、他にどうしようもなくてこの超荒技を繰り出してしまった。
そうしたら、意外にこれで経済が回るようになったという偶然に近い結果に落ち着いた。
以来、景気の状況や金融機関の不良債権の処理状況に応じて、QEを繰り返したことで、市場に余剰資金が生まれ、それが株式投資や新興国投資へと流れた結果、気がつくと10年間上げっ放しという、金融相場となったわけです。
世界を覆う金融緩和の歪
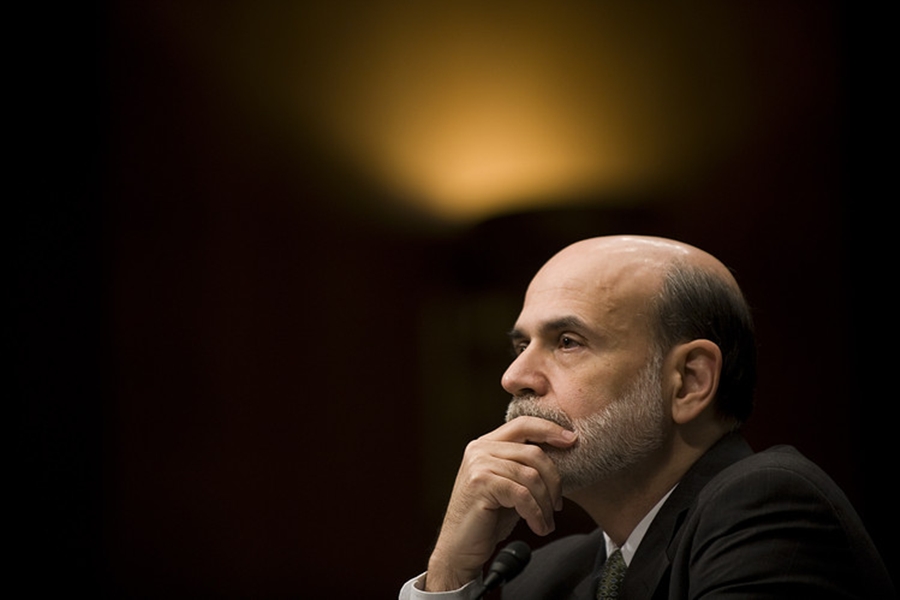
経済が回り始め、投資効果が出て満足できるリターンが得られるようになると、再投資されるのはもちろんだが、事業が拡大することで新たな投資が次々に喚起される。
これは真っ当な経済循環なのだが、ある時期を超えると過大投資によってリターンが割に合わなくなるという現象が出てくる。その時に取られるお決まりの行動は、投資を振り替えるのではなく、さらに増額すること。
その繰り返しによってある程度経済は継続して成長するけど、結局はリターン不足は解消できず終焉を迎えてしまう。
ちょうど今はその状況に差し掛かっていると思われる。
過大な投資を積み上げてきて、経済成長が(米国の場合)3%程度で、金利が2%あると、当然のように積み上げた投資は「過大」と評価せざるを得ない。
しかし、利下げをすれば、再び過大投資に拍車がかかってしまい、それでも3%成長が限界であるなら、状況はますます悪化してしまう、というのがFRBの抱えるジレンマです。
そしてもちろん、世界各国が事情は異なっても、同じようなジレンマに陥っている。
中国経済という砂上の楼閣
こうした極めて微妙なはずの経済運営が、10年間も安定的に株価を押し上げることができたのは、中国と言う突出した成長エンジンがあったからだ。
中国は過去30年間でそのGDP規模が約15倍になり、日本を抜き去って世界第二位のGDP規模になった。その中国の成長力をリーマンショック後、先進国が利用してきて「砂上の楼閣」と言えるほどの過大な経済にしてしまったと言える。
すでに資本主義下であるなら2014年には破綻していると言われる中国経済だが、共産主義下の統制経済であるがゆえに、債務評価を無視した経済システムが、見せかけ上機能してしまっている。
しかし、砂上の楼閣であるなら、土台が崩れ始めたら、無残だろう。
GAFAのような成長エンジンがない
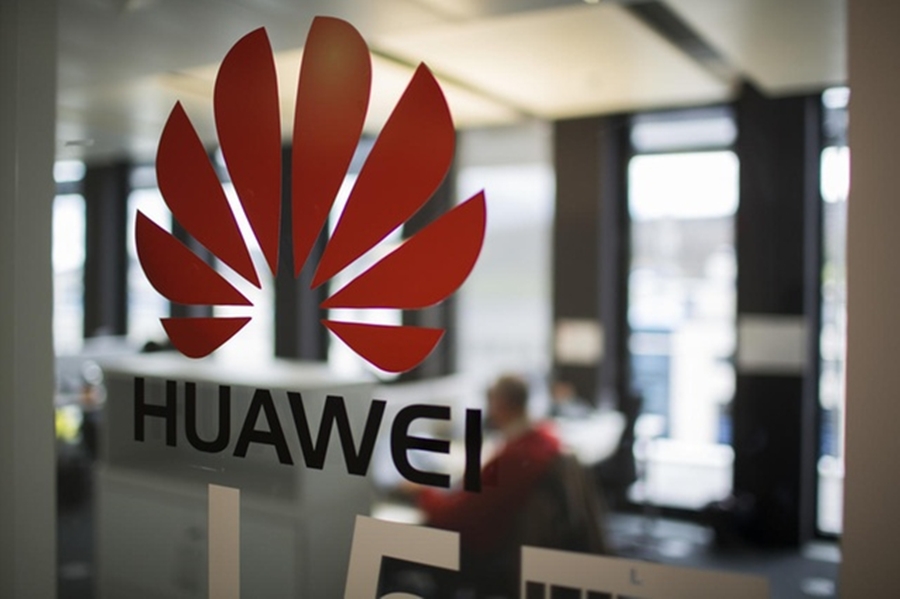
好調に推移していると言われる米国経済は、リーマンショック後イノベーションによって経済をけん引してきたGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)のような先端企業の伸びが頭打ちになると予想されている(一部はなっている)。
そして次世代の牽引役を見いだせないでいることが、米中対立のきっかけの一つと言われている。
GAFAの基本技術は2000年代のもので、すでにイノベーティブではない。そこに中国が模倣と盗用で割って入り、さらに5G分野では米国を凌駕するまでになったことへの危機感は半端なものではないだろう。
米中対立は必然だった
ビジネスマンであるトランプ大統領は、政治を経済に置き換えて考える人。徹底した拝金主義者のように見える。そのトランプ大統領にすれば、米国の技術を模倣・盗用する中国を許せるはずがない。
しかし、中国をここまで引き上げたのは、他でもない米国であると言う事実も現在のジレンマの一つだ。
一方の中国は、長い間米国の政治をカネで買ってきた。クリントンからオバマに至る民主党政権は、中国マネーによって「ある意味売国」していたと言える。
そうした状況が前提となっているだけに、現在の共和党政権と中国の対立構造は根が深い。米国はかつて日本経済にストップをかけたように、中国もまた打たれることは確実だ。
米国にとっての「出る杭」なのだ。
トランプという諸刃の剣

トランプ大統領の評価軸は「米国にとって有利ならYES、振りならNO」と至って明快だ。そして政治的な判断がビジネスに偏り過ぎる人であるがゆえに、経済はもっと良くなり、株価は上昇すると信じている。
米国が利益を独占することで、米国経済は格段に成長できると主張するが、米国が今日の状況になった原因を顧みることはない。
なので、共和党政権として強いアメリカを実現しなければならず、中国に脅かさせることなど到底容認できない。
従って中国は日本のバブル崩壊のような道筋をたどらざるを得ないと思う。
しかし米国もまた、中国と言う成長エンジンを失う過程において、現状の好景気を維持できると考えているとしたら、それは大きな間違いだと思う。米国の産業は、一部のハイテクや軍需を除いて空洞化している。日本が国内回帰をしようとしてもできなかったように、米国はもっとできない。賃金水準が高すぎるからだ。
5年間下げっぱなしの相場が来る予感
QEによってリーマンショック以前の4倍に拡大したマネタリーベースとそれを背景にした過大な投資。今の米国経済がバブルか否か、という点には議論がある。しかし、債券の膨張ぶりからして、企業の投資は明らかに過大投資だ。
そして、投資に見合ったリターンが得られなくなれば、債券市場は巻き戻しに突入する。
米中対立の結果、多くの投資が棄損される可能性は極めて高いはずで、中国経済の縮小や場合によっては崩壊が、理由になることも十分に有り得る。
米国は中国に対して5G関連だけでなく、半導体の禁輸を一部開始した。半導体の中国消費量を考えると、その影響は甚大となる可能性は否定できない。
昨年秋からの下落のきっかけは半導体に対する懐疑が原因だったことを考えると、現状は極めて危険な状況と言え、株価は米中対立を再評価するだろう。
買いで儲けた10年は終わる
昨年(2018年)9月で天井を打ったと思っていた米国市場が、この6月に史上最高値に肉薄(ダウ)し、S&P500は史上最高値を更新した。
こうした巻き戻しは金融相場ならでは、の動きだと思うけれど、企業業績は日米ともに4月以降悪化しているのは明らかで、米国企業の決算が集中する7月、そして日本企業決算の8月は相当に厳しい相場展開になる可能性が高い。
しかも米中対立の深刻化は、今後の株価にかなり悪影響が出るはず。となると、たとえ7月に米国で利下げがあったとしても、日本市場は厳しい状況に陥ると思う。
そして買いで儲けた10年は終わると思う。
短期間での資産形成のために学んでおくべき投資手法を知るなら
無料なら試すべき中小型株投資
-
前の記事

解散・増税延期できなければただの人という話:6月25日(火)後場 2019.06.25
-
次の記事

安倍爆弾は投下されるのか?衆議院本会議:6月26日(水)前場 2019.06.26